8時間+8時間+8時間
賛否あると思いますが、僕は1日3食食べることよりも、1日2食の方が健康的に生きられると思っています。
というよりも、1日○食と決めるのではなく、1日の中で固形物を食べない時間を15時間(オートファジーの考え方は16時間)程度作ることが健康の源だと思います。
1日8時間睡眠するとすると、残りは16時間なので、8時間を自由に食べる時間、残りの8時間を固形物を食べない時間帯と設定すると、比較的実行しやすいと考えています。
そもそも1日3食は過食になりやすい
成人の基礎代謝は平均的には女性が1200kacal、男性で1500kcalです。
一方で、一般的な定食は1食で800kcal程度ありますし、唐揚げ定食やとんかつ定食だと1000kcalを超えるものはザラにあります。
参考までに大戸屋の「鶏と野菜の黒酢あん定食」というまあまあ健康そうな定食が992kcalだそうです。

朝と夜を控えめにして、300calずつに抑えたとしても、基礎代謝を超えてしまいます。
まして、朝はともかく夜ご飯を300kcalに抑えるなんて難しい!と考える人は多いんじゃないでしょうか?
毎日運動している人なら問題ないかもしれませんが(30分のランニングの消費カロリーは250kcal程度)、
多くの人にとって1日3食は単純に考えて食べ過ぎの部類に入ってしまうと思います。
空腹時間を設けるメリット
1日3食食べることが過食になりやすい、一方で、1日2食などにして空腹時間を作ることにはプラスの効果もあります。
胃腸に負担をかけない
消化はとてもエネルギーを使うことはよく知られていることだと思います。
また、以前の酵素の記事でも書いたように、消化にエネルギーを使ってしまうと体の代謝が進まなくなってしまいます。
1日の中の空腹時間は主に胃腸の休息時間となり、疲労回復や代謝の促進につながります。
オートファジー
人間の体内に蓄積できる糖の量は決まっているので、最後にエネルギーを摂取してから10時間が経つと脂肪の分解がより進みます。
また、16時間経つとオートファジーが働くとされています。
オートファジーとはギリシャ語が語源で、auto(自ら)、phagy(食べる)という意味です。
生物が自ら古くなった細胞内のタンパク質分解し、それを栄養源にし新たな細胞を作るシステムをオートファジーと呼びます。
個人的には胃腸への負担軽減の方が効果は大きいと思っていますが、オートファジーを気にする方は16時間(8時間+8時間)の空腹時間を作ることをオススメします。
「○時〜●時までは食べない時間帯」を決めよう
1日は24時間なので、8時間+8時間+8時間に分けることができます。
8時間は睡眠と考えれば、この時間と合わせてもう8時間何も食べない時間を決めれば、16時間断食はやりやすくなります。
例えば、19時までに夕食を食べ終え、朝食を抜き翌日11時まで何も食べなければ16時間断食ができます。
11時〜19時までの間の8時間は好きなものを好きなだけ食べて良いとすれば頑張れそうです。
それに、これを習慣にしてしまえば、人間は意外と簡単に慣れてしまうものです。
どうしてもお腹が空いた時はコールドプレスジュース
とは言っても、お腹が空いてどうしようもない時はあります。
そんな時はコールドプレスジュースがおすすめです。
何より、胃腸に負担をかけない時間帯が大切なので、胃腸への負担なく栄養源を摂取できるコールドプレスジュースが重宝されます。
毎日、厳格にこの食生活を守る必要は全くありませんが、できることから始める、毎日でなくても習慣にして継続することがとても大切です。
最初は1日16時間が難しいかもしれません、その場合は1日12時間の空腹時間から始めてみるのもとても良いと思います。
1日3食きっちり食べるという当たり前のような食生活が、正しいとは限りません。死因に占める生活習慣病の割合は便利な現代ほど多くなっています。
当たり前を見直し、1日の中に胃腸を休める空腹時間をぜひ作ってみましょう。
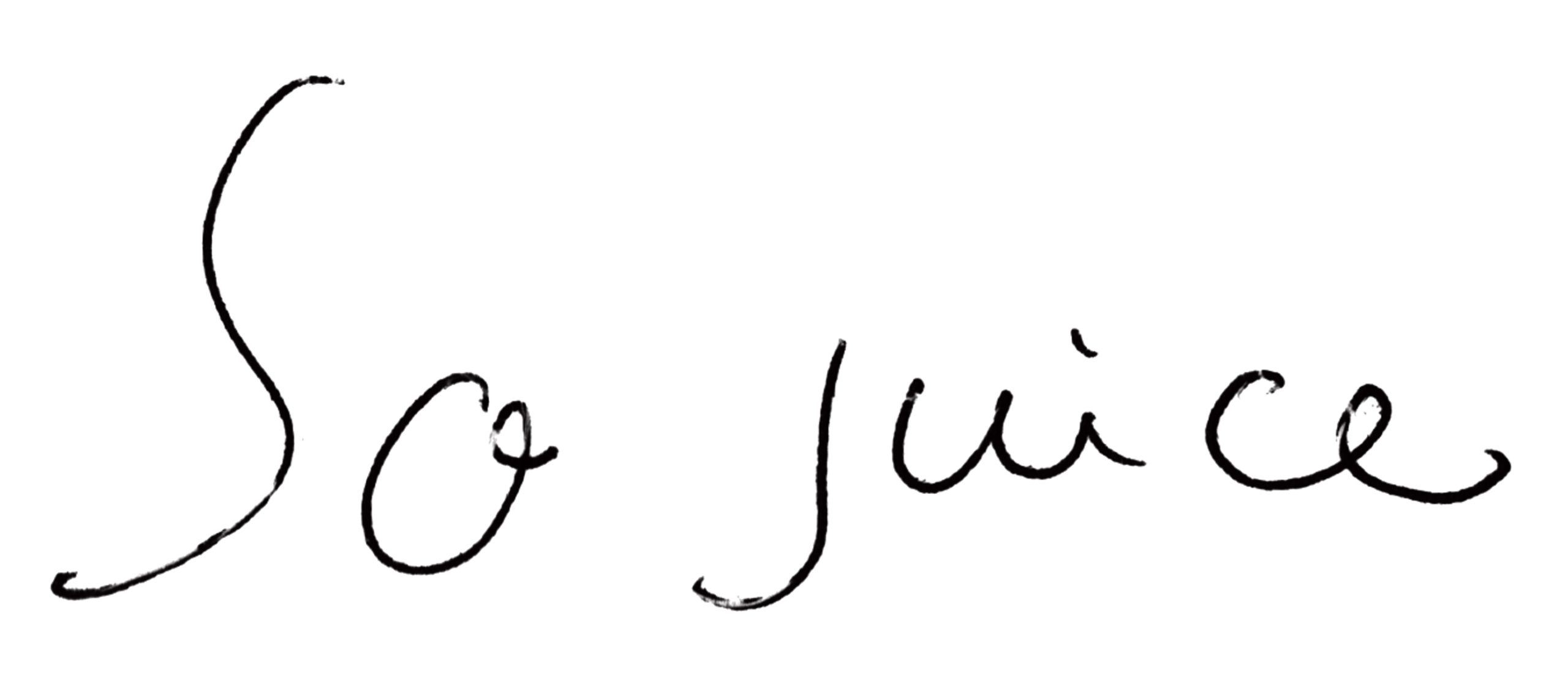
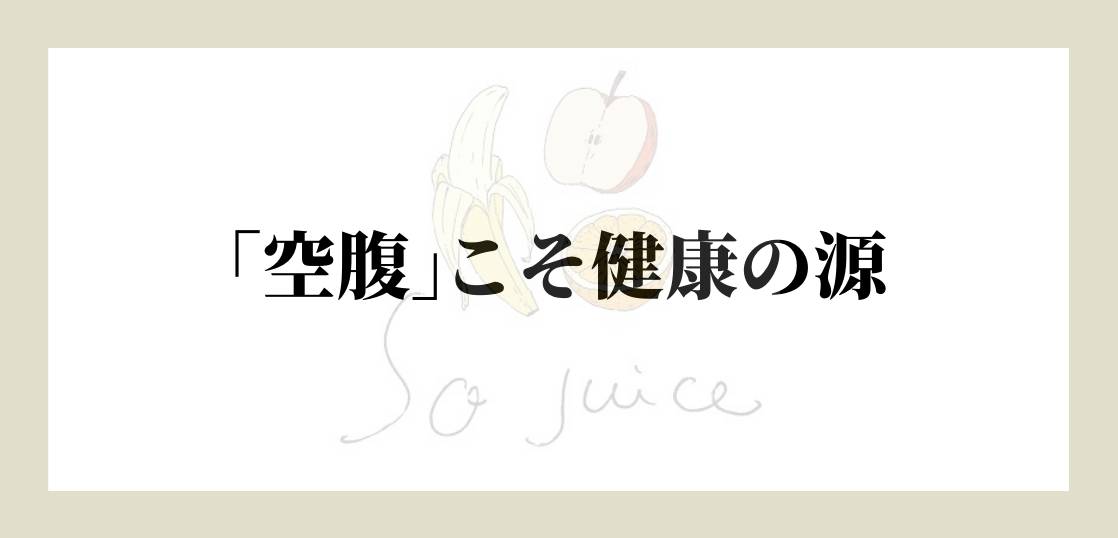
コメントを残す